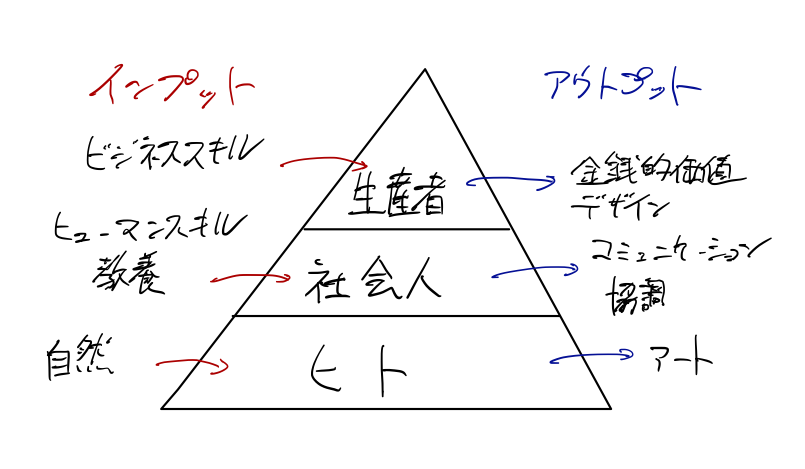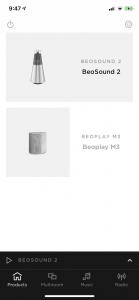7/9〜12の4日間、香港で開催されたRISEに参加してきたので、その様子をざっくりレポートします。
What’s RISE?
2016年に初めて開催され、今年で3回目となるテックイベント。2009年にスタートし、世界最大のテックイベントと称されるWeb Summit からアジア版として派生した模様。
イベントのフレームはWeb Summitを踏襲しており、
4つの大ステージで開かれるトークセッション
企業スポンサードのワークショップ
スタートアップ企業の展示ブース
が主なコンテンツになっていた。
South by Southwest(SXSW) 等のイベントとおおよそ似た構成だが、SXSWはプロダクトの披露がメインのお祭りイベントなのに対して、RISEは投資家とのマッチングはもちろん、急拡大マーケットのど真ん中で実際にビジネスのグロースを狙った鼻息の荒い参加者が多い印象だった。
印象的だったセッション
The China Internet Report
“Visible Hand”
アダム・スミスが提唱した「見えざる手」の理論に対し、中国では政府が方針を明らかにし、その通りに経済が動いていく。そのため、AIなど国の注力分野が非常に力強く急速に成長している。
日本で起きている「AIブーム」とは異次元のレベルで成長している。
From Tinder to Investor: The Story of Sean Rad
“You really have to love what you do”
The Next Frontier of Artificial Intelligence
中国搜狗社が開発するAIを使い、中国語のスピーチをリアルタイムに音声認識&英語翻訳し、英語の字幕がスクリーンに映し出されていた。
Building a Billion Dollar Company
“Traditional Smartphone”
折り曲げることのできるスマートフォンを手首に巻きながら、一般的なスマートフォンを過去のものとして語っていた。
日本からは、LINEの出澤氏とmixiの多留氏が登壇されていた。が、その他のスピーカーが大きなビジョンや最先端の技術を披露していたのと比較すると、既存事業のカイゼン計画程度のスケールに留まっており、インパクトに欠けているように感じた。せめてプレゼンは英語で行って欲しかった。
(同時通訳は入っていたものの、日本語でプレゼンが始まった瞬間に席を立つ来場者が多かった)
会場の様子
展示ブース
正確な数は把握していないが、おそらく100枠以上のブースに3日間日替わりでスタートアップ企業が入り、各々サービスのデモを行っていた。
地元香港の企業を中心に、アジア諸国の企業が多くを占めていたが、アメリカやヨーロッパ、特に南米や東欧の企業も多く出展していた。残念ながらその中に日本の企業を見つけることはできなかった。
アメリカORIG3N 社のブースでは、無料でDNA検査を受けることができ、多くの人が集まっていた。後日専用のアプリに検査結果が送られてくるようなので楽しみ。
ワークショップ
Amazonは専用のワークショップスペースで絶えず開発者向けのawsワークショップを行っていた。
BRIGHTLINE による、アイデアをアイデアで終わらせずに実行まで落とし込むためのワークショップに参加したが、耳の痛い内容が満載の有益なワークショップだった。
驚くことに彼らはそれらのリソースを無償で配布している。興味のある方はぜひアクセスしてみて欲しい。
Brightline Initiative | Bridging The Gap Between Strategy Design and Delivery
海外の大学や機関では同様に有益なリソースを無償で配布するケースが増えているが、もちろん全て英語で書かれている。英語を読めるのと読めないのでは、アクセスできる情報に大きな格差があることを再認識させられた。
ネットワーキング
RISEではネットワーキング(人脈形成)にもかなり力を入れている印象を受けた。
首に掛ける参加証にプリントされたQRコードを専用のアプリで読み取ると、簡単にコンタクト登録することができる仕組みになっており、会場のいたるところでスキャンする姿を見かけた。もう名刺交換の時代は終わったのかもしれない。
また、Night Summitと称して公式のネットワーキングパーティーが毎晩蘭桂坊(ランカイフォン) エリアで開催されていた。前夜祭では参加者を複数のグループに分け、一定時間毎に次の会場に移動して多くの参加者と知り合う仕組みになっている。
アルコールが回ると次第に移動が滞り、最後にはそのエリアの路上全体がパーティー会場と化していた。
世界中のスタートアップが集まり、国籍関係なく交流しているしている様子を見ていると、まさにこれからアジア市場が世界の中心になっていくのだなと感慨深かった。
残念ながらここでも日本人には一人も出会わなかった。
イケているポイント
国内でも多くのイベントが開催されているが、それらと比べて優れているUXをいくつかピックアップしてみた。
専用アプリ
他のグローバルイベントでも一般的になりつつあるが、やはりトークセッションのスケジュールや登壇者の情報を見たり、参加者同士で繋がったり、スマートフォンのアプリでできてしまうのは非常に便利。
未だにひたすら名刺交換を求められる国内のイベントはぜひ導入して欲しい。
メルマガ
当日のカンファレンスのまとめやお得な情報が、必要な情報を適切なタイミングで、さらにビジュアルを駆使したメールで送られてくるので、鬱陶しいという感覚が全くなかった。
動画アーカイブ
メインステージで行われたセッションが全てYouTubeにアップされている。参加者だけにしか見せないといったようなケチくさいことは言わず、有益なコンテンツを多くの人に公開し、本気でマーケットを盛り上げていこうという気概が素晴らしい。
RISE 公式YouTubeチャンネル 告知
会期が終わった途端、Webサイトは来年度の募集に切り替わり、先行割引チケットのお知らせが届いた。もちろん最もテンションが上がっているタイミングなので、「来年も行くぞ!」と申し込んでしまいそうになる。来年は行くなら出展社、もしくは登壇者として行きたいと思うので、まだ検討中ではあるが。
まとめ
RISEのために久々に香港に滞在したが、急拡大マーケットであるアジアの中心に世界中から人が集まり、非常に高い熱量を感じた。
一方、そこにほとんど日本人や日本企業の姿はなく、存在感の無さに大きな危機感を感じた。欧米諸国に「視察」に行くのは構わないが、忘れてはならないのは日本もアジア諸国の一つであり、目の前に巨大なマーケットが存在していることだ。
縮小する国内市場に閉じこもり、欧米の5年落ちのビジネスモデルでパイの奪い合いをすることはそろそろ終わりにし、自分達の持っている価値を見直し、アジア及びグローバル市場の中でどういう役割を担っていくのかを考える必要があるのではないだろうか?