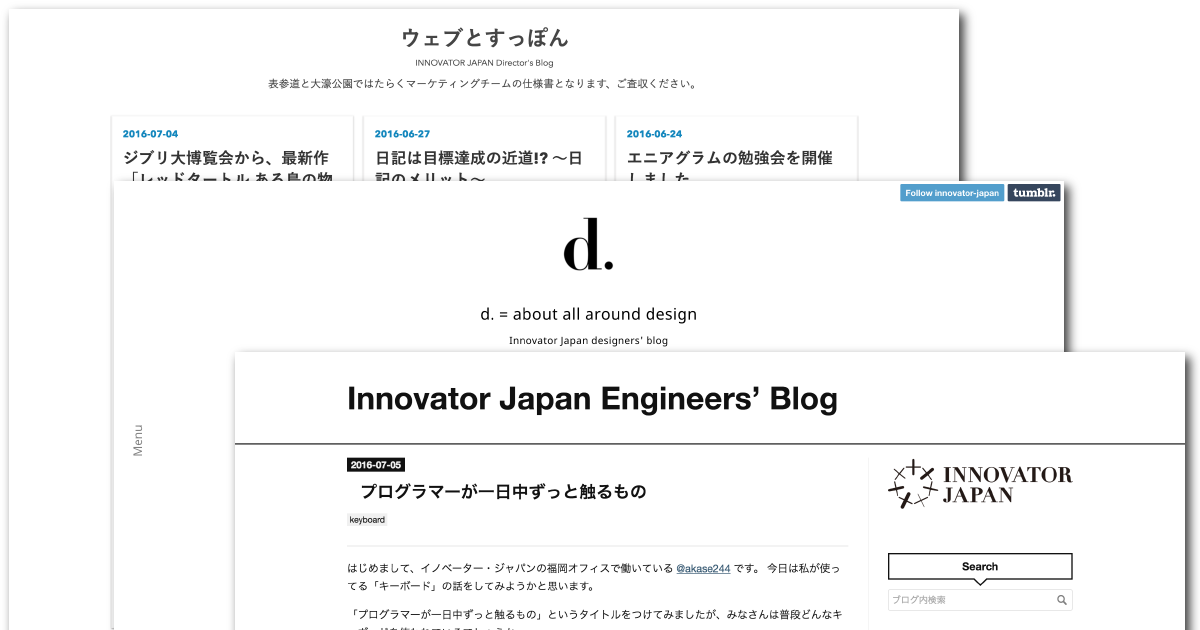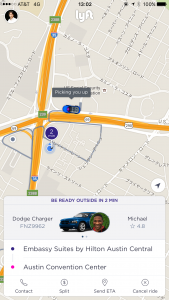South By Southwest(以下、SXSW)に初参加してきました。(文末にフォトギャラリーあり)
SXSWとは、
アメリカ テキサス州のオースティンで毎年開催される、映画・音楽・インタラクティブメディアの祭典。今年で30年目を迎え、世界中から約8.5万人が集まった模様。
今年の目玉コンテンツはオバマ大統領による基調講演。これからの社会におけるデジタルテクノロジーの重要性を説き、政府も率先して取り組んでいることを強調していた。米国の広報戦略のうまさもさることながら、トップがしっかりテクノロジーを理解し、自分の言葉として話せるところは日本が見習わないといけないところ。
また、個人的にはX JAPANのドキュメンタリー映画「We Are X」の上映会に参加できたのが大きな収穫だった。何を隠そう初期の頃からのコアなファンなので、涙なしには観られなかった。3/18にはYOSHIKIのライブパフォーマンスがあったのだが、これには残念ながら参加できず。
まあ、SXSWのコンテンツに関しては各所でレポートされているのでそちらに譲るとして、ここではイベント運営や現地のカルチャーなどバックステージの部分にフォーカスしたいと思う。
ちなみに、月刊「事業構想」4/1発売号にIMJ江端さんと共著で取材記事を書かせていただいたので、そちらもご参照ください。
ベンチャーの登竜門 ツイッターに続く成長株の企業は?
イベント運営

SXSWに限らないかもしれないが、とにかく規模が大きい。動員数だけで言えば日本国内のイベントでも大きいものはあるが、街全体がお祭り状態になることはあまりないと思う。オースティンのダウンタウンエリアはそこまで広くないものの、町中のホテルやレストランがほぼ全て会場になっている。
SXSWが世界中から人を集め、町中のホテルが満室になり、郊外のホテルにも人が溢れるから交通機関も潤い、数百のカンファレンスを運営するために膨大な数の学生がボランティアとして参加している。もはや単なるイベントというより、オースティン市の一大事業のレベルに達している。
SXSWの影響もあってか、ここ数年オースティンを拠点とするスタートアップ企業が増えているらしい。ニューヨークやサンフランシスコの物価が高騰しているため、生活コストが低く温暖な気候のテキサスが人気とのこと。
一方、SXSWのブランドが確立されてきたために、出展料が高騰しているという情報もあった。サンフランシスコの某企業から参加されていた方は「ここ数年毎年出展していたが、今年は出展を見合わせた」と話しており、出展社の顔ぶれが変わり「昨年より劣化した」という意見もあった。30周年を迎える今回が何らかの転機になるのかもしれない。
現地のカルチャー
食
現地の人々におすすめを聞くと、ほぼ100%「バーベキュー」と「テキシカン」という答えが返ってきた。
バーベキューは日本でもよくやる「BBQ」とは違い、豪快に焼く肉料理のこと。テキシカンはテキサス風メキシコ料理のことを言うらしい。南に下ればメキシコとの国境なので、たしかに街中にはメキシコ料理店が多く、滞在中もかなりの頻度でメキシコ料理を食べていた気がする。バーベキューについては、行く店によるのかもしれないが、正直日本で食べる肉の方がはるかに美味しいと感じた。
住・交通
イベント会期中はホテルはどこも満室だった。SXSWが仲介してホテルの予約ができるのだが、チケット販売当日にダウンタウンエリアのホテルは売り切れてしまうらしい。そこで大活躍なのがAirbnb。日本ではまだグレーゾーンだが、こちらでは一般的に使われている。会期中は値段が高騰するため、自分は旅行に行ってでも家を貸し出して小銭稼ぎをする人も多いらしい。台湾から参加していた友人グループは4人で高級マンションをシェアしていたが、ホテルよりもはるかに安く借りられていた。
自分はダウンタウンから10kmほど離れた郊外のホテルに泊まっていたのだが、日々の交通手段として使ったのがLyft。東京でも微妙に使われているUber(正確に言うとUberではなくUberX)の対抗馬。今回、LyftがSXSWの公式スポンサーということで、参加者全員に$10程度のクーポンコードを配布していたりLyft推しな雰囲気だった。

Lyftは日本で言うところの白タクで、一般人がドライバー登録をして客の輸送をしている。そのため車種も様々で、今回乗ったのはトヨタのカローラからDodgeのスポーツカーまで様々だった。ちなみに、多くのドライバーはLyftとUberXの両方にドライバー登録しており、状況によって使い分けているとのこと。ただ、運営会社に支払うマージンがUberXが25%なのに対してLyftが20%らしく、どのドライバーもLyftを推していた。みんなコミュニケーション能力が高くて目的地までのトークが楽しく、乗車後の評価は毎回★5つにしてしまった。
Lyftだけで生計を立てているドライバーも多いようで、スマートフォンが新しい職業を生み、人々の生活を変えているということを改めて感じさせるサービスだった。こういったイノベーションにいつもブレーキがかかる日本がもどかしい。
[gap]
といった感じでSXSWに行ってイベントそのもの以外からも色々と刺激を受けてきたわけだが、逆にもやっとした焦りのようなものも感じた。SWSXで見て聞いてきた多くの会社が、世界中の人材とコラボレーションしながらチャレンジし続けている状況の中で、自分たちは日本に安住し過ぎていないかと。今回、日本からブース出展している会社は少なからずあったものの、個人的には世界の大きな動きに取り残されているような感覚を受けた。
一方、堂々と話されたり展示されたりしていても、まだ構想段階であったり、正直なところイマイチと感じるものも多かった。真面目につくって実現段階まで持っていっても、最終的に世の中に伝わらなければ無いのも同然ということを考えると、実はこういったプレゼン先行型が勝ち組になっていくことが多いのかもしれない。
であれば我々も構想やプロトタイプ段階のサービスをもっとアピールすべく、来年あたりSXSWに出展するのもあり、かな?
[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail”]