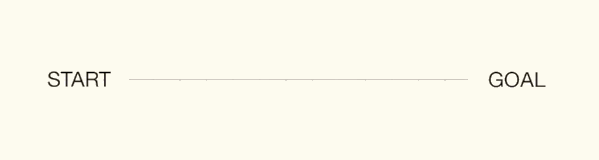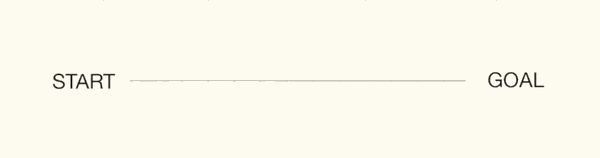これからの経済成長の中心と言われるインド。今回初めて事業展開を見据えて出張してきました。これまで数多くの国を訪れた中でも、トップレベルの「刺激」を得てきたので備忘録としてまとめておきたいと思います。
背景
イノベーター・ジャパンは、創業時からグローバルにビジネスをする事をビジョンに掲げています。
1つ目の理由は、IT、特にインターネットを主なツールとした事業を展開するのに際し、「ボーダーレス」というインターネットの強みを生かさない限り、そのメリットが半減してしまうと考えているからです。巨大な市場規模と保護政策がある中国のような特殊なケースはあるものの、国内市場に限定したサービスが、間も無くグローバルプレーヤーに駆逐されるという事例を数多く見てきました。
2つ目の理由は、グローバル水準に社員の待遇を上げたいからです。グローバル市場で競争力のあるサービスを日本人だけでつくるのはほぼ無理だと考えています。多国籍チームをつくるにはグローバル水準の待遇が必要不可欠です。しかしながら、残念なことに国内ではITやデザインに対する価値付けが非常に低く、同じアウトプットでも得られる対価が大きく異なることが多々あります。もちろん国内でも価値を認めてもらえるような活動は続けていくものの、同時にグローバル市場でチャンスをものにしていくチャレンジが必要だと考えています。
イノベーター・ジャパンは、Innovator in JapanとJapan as Innovatorの二つの意味を社名に込めていますが、日本に埋もれた価値を見出し、磨きをかけ、ニーズと結びつける先として、これから世界経済の重心となると思われるアジアマーケットに注目しています。
ビジネスフィールドとしてのインド
一言でインドと言っても、面積にして日本の約8.7倍、人口では日本の10倍を超える広大な国です。さらにそれぞれ言語も異なる29の州からなり、ヨーロッパや南米と同レベルの「諸国」と言った方がニュアンスとしては近いかもしれません。今回は時間的な制約もあり、デリー周辺しか訪問できなかったのですが、次回はぜひ他のエリアにも行ってみたいと思ってます。
今回訪れたデリー(内陸北部)とムンバイ(西海岸)が2大都市で、政治の中心であるデリーに対して、ムンバイは商業の中心だそうです。中国で言うところの北京と上海といったところでしょうか?
デリー単体だと、ほぼ神奈川県の面積と同じで、人口密度は東京の2倍。インド門(India Gate)を中心に放射状に広がった街でした。その隣には、外資系やIT系企業が集まるグルガーオン(Gurugram / Gurgaon)とメディア系や工業系企業が集まるノイダ(Noida)という街があります。いずれも車で渋滞が無ければ20〜30分(渋滞だと2時間以上かかることも…)という距離感です。ここでは訪問した個別企業については割愛しますが、今回グルガーオンとノイダを中心に商談をして回りました。

個人的な感覚だと、グルガーオンは東京における幕張新都心をさらに進化させたような雰囲気で、新しい大きなビルがいくつも立ち並んでいました。このエリアだけで既にWeWorkが3拠点もあり、多くのスタートアップが集まっているとのこと。日系企業もここにオフィスを構える企業が多いそうです。

聞くところによると、このエリアに立ち並ぶマンションは東京の高級マンション並みかそれ以上の値段とのこと。約10年前にはほぼ何も無かったそうなので、いかに急速に成長している都市なのかがわかります。

一方、ノイダはかつて治安が悪いエリアの代表格だったそうで、今でも家賃も他のエリアと比較するとだいぶお手頃だそうです。未だに道路の舗装も十分にされておらず牛が横たわっているようなエリアがありつつも、驚くことに門を一つくぐると近代的なコワーキングスペースがあったりします。まさにカオス!
また、デリーのインディラガンディ空港のすぐ隣には、その名の通りエアロシティ(Aerocity)というエリアがあり、まるでオアシスのように外資系の高級ホテルが立ち並んでいました。街中ではあまり見かけないようなスーツ姿のビジネスマンが多く、ホテル内で商談を済ませるケースも多いそうです。ちなみに、このエリア以外では全く日本人に遭遇しませんでした。
IT先進国としてのインド
よくインドにはIT技術者が多いと言われますが、IT技術者は未だに残る身分制度に縛られることなく出世することができるため人が集まりやすいといった背景があるようです。実際、海外企業からシステム開発を受託する会社が多く存在し、特に英語圏の企業では社内で仕様を決めた上でこういった会社に開発を発注することが一般的になっているようです。
しかしながら、多くの日本の企業には「システム開発をインドにアウトソースして品質は大丈夫なのか?」といった不安が未だにあるようです。結論からすると、そのような不安は杞憂である可能性が高いです。ソフトウェアの開発行程や品質の管理について実際に画面を見せてもらいましたが、国内の大手SIerと同等かそれ以上の管理がされていました。もし、開発のアウトソースがうまくいかないとすると、発注企業の要件定義やコミュニケーションのスキルの低さが主因になっているかもしれません。(国内企業は「何となくいい感じにつくって」的なオーダーが…)
また、IT技術者が多いことのメリットとして、どの企業も社内に人員を抱えてシステム開発を内製できているという点です。システム開発を外注することのデメリットとして、どうしても開発速度が遅くなったり、プロトタイプ開発がしづらかったりという点がありますが、今回訪問したいずれのスタートアップ企業もシステムを内製していました。さらに、インドのトップクラスの大学でコンピューターサイエンスを専攻したエンジニアが当たり前のように最新の言語やフレームワークを使って開発しており、アメリカ西海岸で活躍している精鋭たちも含めるとどれだけのポテンシャルを秘めてるのかと、正直ショックを受けました。
ITの利用サイドにおいても、Paytmを代表とするキャッシュレス決済が一般的になっていたり、Uberが街中に走っていてどこにいてもすぐにつかまるような環境でした。インドでは4Gのネットワークがかなり普及しており、さらにそれを格安で利用できるため、低所得層でもスマートフォンを持っているのが当たり前だそうです。

日本と比較するとまだまだ公共インフラは整備されていない点が目立ちますが、ITインフラについては日本よりも普及している点が多そうです。逆に、日本は公共インフラの整備に対して、ITインフラの普及が異常に遅れていると言った方が正しいのかもしれません。
生活拠点としてのインド
今回なんと言っても一番苦労したのが原因不明の腹痛でした。到着翌日から帰国後までずっと続いた下痢を伴う腹痛。「インドに行くとみんな腹壊すから気をつけて」と言われつつ出発したものの、これまで中国を含めて数多くの国に出張したけど特別体調を崩したこともないので、「まぁ大丈夫でしょ」と油断していたら見事にやられました。もちろん、ミネラルウォーター以外の水は飲まないように気をつけていたし、特別に辛いものを食べたわけではないけど、断続的に腹痛が発生してトイレに駆け込んでいました。日本のようにそこら中にトイレがあるわけではないので、トイレに対する不安にボディブローのようにMPを削られていました。
帰国後にWebで原因を探ると、日本人の胃腸はマサラ(香辛料)に対する耐性が弱いために消化不良を起こしやすく、体調を崩しているところに少しでも大腸菌などの病原菌が入ると胃腸炎になってしまうそうです。そして、インドを初めて訪れる日本人の多くはこの症状になるため、「インドの洗礼」と言われているそう。インドの洗礼に日本の正露丸は勝つことができませんでした。
そんなインドの洗礼を受けつつも、2〜3日滞在すると「しばらく住んでみたら面白いかも」と思える位に馴染んできました。道路には車と人が入り乱れてみんなクラクション鳴らしまくりだったり、そこら中に野良犬や野良牛がいたり、正直多くの日本人にとってはストレスフルな環境だと思います。しかし、たまにそのような環境に身を置いた方が、清潔で安全な日本の環境に慣れて鈍感になっている「野生の生存本能」を研ぎ澄ますことができると考えています。自分にとっては、野生の生存本能を活性化することがビジネスデザインに必要不可欠になっているのかもしれません。
住環境はどうかというと、ひとつの街にバラック小屋から超豪華なお屋敷まで存在しており、貧富の格差が日本の何倍も大きい印象でした。今回、当社社員の実家にもお邪魔しましたが、広々としていて非常に快適な空間でした。デリーには大型ショッピングモールも複数あり、Uber等の交通網を鑑みると生活拠点としても十分なレベルにあるかもしれません。
まとめ
日本にいるとインドがどんなところなのかよくわからないかもしれません。もしかすると、ガンジス川の沐浴のイメージだけで、まだまだ途上国だと認識している人の方が多いかもしれません。しかし、インドの多様性においてそれはほんの一側面に過ぎず、他の側面では急速な経済成長の中で東京を上回るようなエリアもあるというのが現実のようです。
スタートアップ企業についても、強烈なハングリー精神と開発力ですでにサービスを世に出し、世界のマーケットを虎視眈々と狙っている企業が山のようにいます。
その中で我々イノベーター・ジャパンは何をしたいかと言うと、別に国単位の競争をしたいわけではなく、国を越えた適材適所、価値とニーズを結びつけることによってワクワクとハッピーの最大化をしたいのです。
日本に埋もれた価値を磨いて海外に持っていくことも、海外のスタートアップと一緒に日本の課題解決をすることも、もちろん自社のサービスをグローバル展開することも、我々自身がワクワクすることをし続けたいと考えています。
「アジア市場」はなぜか日本だと他人事のように語られがちですが、日本もアジアの一部です。せっかくのお祭りなので、現状の安定(安定=退化の始まり)に執着することなく積極的に乗っかったらいいのではないでしょうか。
もし、そんなイノベーター・ジャパンがご一緒できることがあれば、もしくはチームに入って一緒に何かしたいという方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご連絡ください。